水路・樋門

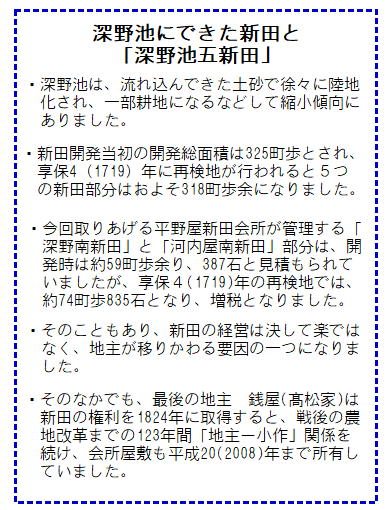
深野南新田」と「河内屋南新田」の 樋門・笠石
① 満島樋(みつしまひ)
深野南新田の最南端にあり、恩智川から水を引き新田内に送る最重要樋門です。昭和30年代、「恩智川(おんちがわ)」の水質悪化によって取水が止められるまでの250年間、深野南新田の大半の用水をまかなっていました。撤去の動きが起きたとき、地元の努力で、新田の歴史を伝える遺産として、そのままの姿で残されました。弘化五申年(こうかごさるのとし・1848年)の銘があります。写真:大東市HPより


② 落合橋下伏越樋・笠石(おちあばししたふせこしひ・かさいし)
この伏越樋は深野南新田と河内屋南新田の境界になっている「大川(おおかわ)」の下をくぐり抜けていました。現在、伏越樋の両側の笠石が残されています。新田が開発されるとき、新田と近隣の村との取り決めによって、深野南新田は、大川の水は新田側に取り込まず直接恩智川に流すことになりました。そこで、深野南新田は、用水を確保するため大川の下に伏越樋をつくり河内屋南新田の水路と現在の「銭屋川(ぜにやがわ)」をつなげて河内屋南新田からの水を取り入れました。現在は、樋の両側の笠石が残されています。



コラム
この水の道は、年貢米を運ぶなど、河内屋南新田と深野南新田を結ぶ船の道としても使われていました。農作業用の舟が伏せ越し樋をくぐって行き交っていました。伏越樋は役目を終えた現在も、新田の歴史遺産として残されています。写真上の樋門は大川左岸の河内屋南新田側にあり、安政三丙辰三月(あんせいさんひのえたつさんがつ・1856年4月)の銘で、下の写真の笠石には大川右岸の深野南新田側にあり、銘はありません。
③ 待樋 (まちび)
平野屋会所に伝わる開発初期の絵図にはこの樋は確認できませんが、「平野屋会所文書」には、この付近にある樋の話が出てきます。また昭和初期の絵図にも描かれています。現在は、コンクリート製の水門で、使用
されていません。地元の年配者によれば、水位調整に使っていたとのことです。建造年などわかりません。

④ どんばの伏越樋(どんばのふせこしひ)
東側の山間から流れてきた長縄手川(ながなわてがわ:現在の長農川)の水が、旧鍋田川の下につくられたこの伏越樋を通って「四間井路」(現在の銭屋川)に流れていました。新田開発時の近隣村々との約束で、鍋田川の水は直接寝屋川に流すことになっていたため、長縄手川の水を鍋田川と立体交差させました。昭和50年代に、鍋田川が東の方に付け替えられたため、旧河道は道路になりましたが伏越樋は元のままで、現在も役目をはたしています。樋門写真:大東市HPより

⑤ かみなり樋門 (かみなりひもん)
深野南新田を南北に流れる井路(水路)の中央部にある重要な樋門の一つです。この樋門は水路に水をためて「ため池」状態にする重要な役割を持っていました。また、大雨になるとこの樋門を閉じて北側の地域の洪水を防いでいました。年配者に話を聞くと、「樋門当番の時は、雷が落ちる最中でも、この樋を閉じに行かなければならなかった。この樋のある付近はよく雷が落ちて何度か肝を潰した。」と語っていました。嘉永四亥年(かえいよんいのとし・1851年)銘があります.


◎下の写真は、かみなり樋門がある場所への通路入り口付近に設置されている説明板です。(通路は私道ですが所有されている方のご厚意で気を付けて安全に通過するならと了承を得ていますので、話し声や安全に留意して見学してください。)

⑥ 谷川1丁目の樋門 (たにがわいっちょうめのひもん)
この地域の水の流れを調整をしていた重要な樋門の一つです。近くに在ったもう一つの樋門(写真下の樋門)などを加えた樋門群で水路(現在の新堀川)に水を溜めて「ため池」状態をつくり出す役割も持っていました。安政六未年四月(あんせいろくひつじのとししがつ・1859年5月)銘があります。 (説明板がある場所は私有地です。樋門の姿は右側にある鉄橋付近から望めます。樋門写真:大東市教育委員会「石の文化財」より)




⑦ 谷川公民館前庭の樋門笠石 ( たにがわこうみんかんまえにわのひもんかさいし) 役目を終えた二つの樋門の笠石が地元の努力で公民館前庭に置かれています。
一つは、新堀川にあった昭和53(1978)年に撤去された(⑥で紹介した)もので(○形の写真) 、嘉永四亥年(かえいよんいのとし・1851年)の銘があります。もう一つは、新堀川と鍋田川を結ぶ井路(水路)が昭和58年から60年にかけて暗渠になったときに撤去されたものです。
ま た、これらの樋とは別に、近くの地蔵堂の北側に閘門式(こうもんしき)の樋門があって新堀川と鍋田川を結んでいました。この樋門を通って農業用の小舟で鍋田川や寝屋川と行き来していました



⑧ 三反物の樋 (さんたんもんのひ)
この樋門は、満島樋から取り入れられた恩智川の水と落合橋下伏越樋を通って流れてくる水や東側の村から流れ込んでくる水が集まる地点にありました。
この地点は、深野南新田にとって重要な場所であるだけでなく、近隣村々との「水争い」の場所としても『平野屋会所文書』に登場しています。この樋門は、長い間シートで覆われていましたが、令和4年3月にシートが外され再び目にすることができるようになりました。弘化二巳年(こうかにみのとし・1845年)銘があります。
『平野屋会所文書』などの資料には、深野南新田と河内屋南新田にあった井路や樋門の記事がたくさん出てきます。また、会所がある地元平野屋地区に残る「五カ所文書」に含まれる昭和初期の水路絵図にも、樋の場所や用水と悪水(使用済みの水)の流れる方向、洪水時に水を落とし込む場所など描かれています。 大東市教育委員会発行の『平野屋会所文書』(全4冊)『新田庄屋文書』『諸福村東家文書 』『河合家文書』(全2冊)は、教育委員会生涯学習 や大東市歴史民 俗資料館などで購入できます。

⑨ 河内屋南新田に残る 樋 門笠石
河内屋南新田は、深野池が新田に生まれ変わるとき大坂の商人河内屋源七(かわちやげんしち)が地主になり開発されましたが、開発 直後平野屋に譲渡され、深野南新田と共に平野屋新田会所の管理する新田になりました。この笠石は、はじめから現在地にあったかは 分かりませんが、恩智川とつながっていた水路と南に位置する味岡新田(あじおかしんでん)からの水路が合流する場所にあります。 銘は確認できません。

■ その他の樋門 ■
市の生涯学習課の文化財担当やサポーター会議が調べていますが、ほかに何箇所かで石積みと笠石などが確認されています。
また、『平野屋会所文書』などの資料には、深野南新田と河内屋南新田にあった井路や樋門の記事がたくさん出てきます。会所がある地元平野屋地区に残る「五カ所文書」に含まれる昭和初期の水路絵図にも、樋の場所や用水と悪水(使用済みの水)の流れる方向、洪水時に水を落とし込む場所など描かれています。 大東市教育委員会発行の『平野屋会所文書』(全4冊)『新田庄屋文書』『諸福村東家文書 』『河合家文書』(全2冊)は、教育委員会生涯学習 や大東市歴史民 俗資料館などで購入できます。

■当ホームページの写真や資料の無断使用はお控えください。